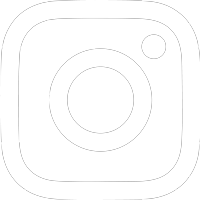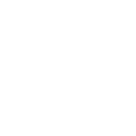第2章|ありがとうが疑いになった日 ある納棺の現場での出来事

ありがとうが疑いになった日 ある納棺の現場での出来事
出張で重ねた納棺の先にあった違和感
岐阜県への一か月の出張。
納棺協会に所属していた私は、現地の大手葬儀社からの依頼を受け、連日納棺の現場に立っていた。
件数は多すぎて覚えていないが、そのうちの八割近くのご家族から寸志をいただいた。
私自身、どの現場でもこの方は自分の母だ、父だという思いで手を合わせていた。
だからこそ、その感謝が寸志という形になったとき、私は純粋にありがたいと思っていた。
お金ではない。気持ちを手渡されたのだと感じていた。
最終日、報告の電話で知らされた疑い
出張の最終日、私はいつものように本社の事務所に電話をし、全現場の終了報告と翌日以降の確認を行った。
そのときだった。電話口の事務員が、支店長と変わる。お疲れ様と…少し言いづらそうに話し出した。
現地の葬儀社から、遺族に寸志をオネダリしているという声があったと聞かされた。
一瞬、息が詰まった。
何も言えなかった。
現場では一切、そんな指摘はなかった
その出張期間中、私は一度も現場でそんなことを言われたことがなかった。
注意も指摘もなく、依頼は淡々と続き、私は真面目に、誠実に現場に入っていた。
誰も、何も言わなかった。
なのに、知らないところでそんな話が出ていた。
その事実に、私は深く傷ついた。
寸志の件数と、記憶に残る金額
何件いただいたのかは、正直もう覚えていない。
ただ一つだけ、今でもはっきりと覚えていることがある。
それは、出張期間中にいただいた寸志の総額が、当時の自分の月給を上回っていたということだ。
もちろん、金額の大小が大切なのではない。
それほどまでに感謝を受け取ったという実感と、それがすべて疑いにすり替わって返ってきたという事実が、何よりも苦しかった。
誰にも言えず、レオパレスの一室で一人考えた
その夜、私は岐阜のレオパレス21の部屋に戻った。
部屋は静まり返っていて、外の気配も感じない。
スマホを持って、ただぼんやりと考えていた。
やっと全て終わったのに、最後にこれか。
泣くでも怒るでもなく、ただ笑うしかなかった。
心の底に、ぽっかりと穴が空いた気がした。
感謝は、時に疑いへと変わる
私は、オネダリなど一度もしていない。
むしろ、いただいたことにさえ慎重で、常に自分の姿勢を見つめ直しながら現場に立っていた。
だが、それでも疑われるのだと知った。
感謝は、誤解される。
信頼は、壊れることがある。
それが現実だった。
それでも、信じたかったもの
それでも、私の心には残っていた。
娘さんのあの言葉
母が若返ったみたいです
手を握って、涙を流してくれた遺族の姿
寸志を渡すときの、あの震える手
私はあの場で、本当に必要とされていた。
そう信じている。
次章へ
出張を終えた私は、予定通り退職を決意した。
それは誤解が理由ではない。
入社したときから、自分で決めていたことだった。
次章では、なぜ私は一年で納棺協会を辞めたのか、
その決断の背景を記していきたい。
相談したい方へ
- LINE公式登録はこちら
→ 「後悔しないお別れ」のために、大切な資料をLINEからすぐにご覧いただけます。
筆者について
樺澤忠志(とーたる・さぽーと0528代表/納棺師)
弘前市出身。父の死をきっかけに葬祭の道へ。今、感情を封じない「喜怒哀楽の家族葬®」を弘前で提供しています。
最期に「ありがとう」が届く時間を。
それが、私の仕事のすべてです。
まだ葬儀の予定がなくても、
今、LINEで「不安」を減らせます。「何を準備しておけばいい?」「費用は?」「誰に頼めばいいのか分からない」
そんな方へ、無料で個別にご相談いただけるLINE相談を開設しています。
まだお急ぎでない方も大歓迎です。葬儀を考える時、
費用でも、形式でもなく、
一番大切なのは、あなたがどんな想いで見送りたいかです。たった3つの質問に答えるだけで、
あなたに合った「後悔しないお別れの形」が見えてきます。
- STEP 1:LINE公式アカウントを友だち追加
- STEP 2:メッセージで「相談希望」と送るだけでOK
- STEP 3:対話形式で、気持ち・状況・準備を丁寧に伺います
▶ お電話でも相談可能です(24時間対応)
0172-82-2078
喜怒哀楽の家族葬® 樺澤忠志の記録|全12章
これは、ひとりの納棺師が歩んできた12の記録。
「形ではなく、感情に向き合う葬儀」を信じてきた私の原点と、実践と、これからの話です。
- 第1章 身内を送るつもりで納棺する
岐阜での出張、初めて一人で任された納棺。家族の涙が、自分の原点となった日。- 第2章 ありがとうが疑いになった日
感謝として受け取った寸志が、誤解を生んだ。納棺師としての信念が試された出来事。- 第3章 1年という期限を自分で決めていた
最初から決めていた「1年間の修業」。納棺協会を卒業し、自分の道を歩き始める。- 第4章 ゼロから始めた 誰も頼れない道を自分で切り拓いた
遺品整理からの再出発。紹介も信頼もゼロの中、弘前で地道に始めた独立の日々。- 第5章 感情を抑えない葬儀を 誰かが始めなければと思った
コロナ禍で失われた感情の時間。「喜怒哀楽の家族葬®」という言葉に辿り着いた理由。- 第6章 ここでようやく、父と話せた気がします
自宅での一日葬。式ではなく、対話の時間が、遺族の心を変えていった。- 第7章 魂の成長としての葬儀
葬儀は終わりではない。「感情に正直になること」が人の魂を深めていく。- 第8章 その日、母が若返ったと言われた納棺の記憶
「母が若返った」――遺族の言葉が、納棺師としてのすべての原点になった。- 第9章 なぜ、今この葬儀が必要なのか
形式ではなく感情を整える葬儀へ。時代が変わり、必要とされている理由。- 第10章 ご家族の声が教えてくれたこと
「こんなに心が動いたお葬式は初めて」──遺族の言葉が、すべての証明だった。- 第11章 これからの供養と、心の居場所について
葬儀は、生きていく人の“心の居場所”をつくる時間。送り方が、生き方を変える。- 終章 最後の時間に 人は 魂の美しさを取り戻す
人は亡くなるとき、もっとも美しい魂を取り戻す。その瞬間に寄り添う納棺師の祈り。▶ ご相談・資料請求は
LINE公式アカウントはこちら(24時間受付)