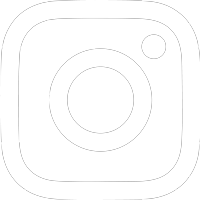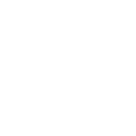第8章│その日、母が若返ったと言われた納棺の記憶

その日、母が若返ったと言われた納棺の記憶
魂に触れた時間が、すべての原点になった
初めて一人で任された納棺の現場
岐阜出張の初日、私は納棺協会に在籍して間もない頃だった
その日、現地で初めて一人で任された現場があった
緊張と責任感が重くのしかかる中
私はただ一つの思いでその現場に向かった
この人は、自分の母だと思って納棺しよう
そう決めていた
亡き母に再会したようです
納棺を終えたとき、遺族が静かに集まり始めた
その中で、娘さんがふとつぶやいた
母が、若返ったみたいです
昔の母に戻ったような気がします
その言葉を聞いた瞬間、私は体の奥で何かが震えた
きれいに整えられた顔ではなく
そこに映ったのは、記憶の中にいる母だったのだとわかった
あの一言には、ただの感謝ではなく
愛と再会と癒しが混ざっていた
整えたのは「顔」ではなかった
私はその時はっきりと知った
私が整えたのは、顔ではない
故人と家族の関係だった
記憶にある母と、亡くなった母がひとつに重なる
その時間こそが、遺された人の「魂の整理」だったのだと
納棺とは、命の終わりを整えることではない
命に関わってきた人たちの感情に、静かに触れることなのだと思った
忘れられなかった理由
私は、あの家族からいただいた寸志も
かけられた言葉も、すべて今も忘れられない
金額でも形式でもない
感情が届いたという確かな感覚がそこにあったからだ
納棺師として生きていく中で
何度も迷いや揺らぎがあった
けれどそのたびに、あの現場の空気を思い出した
自分は、こういう時間を届けるためにこの仕事をしているのだと
魂が触れ合った時間だった
家族の誰かにとって
あの一日が、忘れられない日になることがある
私にとっても、あの納棺は、人生の指針になった
魂に触れた
あの時間に触れた
そう確信できた出来事だった
だから私は、今も手を抜かない
どれだけ多くの現場をこなしても
あの一件の重さを超えることはない
あれが、すべての始まりだった
だから今も、誰であっても
自分の母だと思って
心を込めて手を添えている
いつかまた、あの日のように
家族の誰かがこう言ってくれるかもしれない
母が若返ったようでした
その言葉を、今も私は胸に抱いている
次章へ
次回は、この仕事が必要とされる理由
なぜ今、喜怒哀楽の家族葬が求められているのかを語りたい
相談したい方へ
- LINE公式登録はこちら
→ 「後悔しないお別れ」のために、大切な資料をLINEからすぐにご覧いただけます。
筆者について
樺澤忠志(とーたる・さぽーと0528代表/納棺師)
弘前市出身。父の死をきっかけに葬祭の道へ。今、感情を封じない「喜怒哀楽の家族葬®」を弘前で提供しています。
最期に「ありがとう」が届く時間を。
それが、私の仕事のすべてです。
まだ葬儀の予定がなくても、
今、LINEで「不安」を減らせます。「何を準備しておけばいい?」「費用は?」「誰に頼めばいいのか分からない」
そんな方へ、無料で個別にご相談いただけるLINE相談を開設しています。
まだお急ぎでない方も大歓迎です。葬儀を考える時、
費用でも、形式でもなく、
一番大切なのは、あなたがどんな想いで見送りたいかです。たった3つの質問に答えるだけで、
あなたに合った「後悔しないお別れの形」が見えてきます。
- STEP 1:LINE公式アカウントを友だち追加
- STEP 2:メッセージで「相談希望」と送るだけでOK
- STEP 3:対話形式で、気持ち・状況・準備を丁寧に伺います
▶ お電話でも相談可能です(24時間対応)
0172-82-2078
喜怒哀楽の家族葬® 樺澤忠志の記録|全12章
これは、ひとりの納棺師が歩んできた12の記録。
「形ではなく、感情に向き合う葬儀」を信じてきた私の原点と、実践と、これからの話です。
- 第1章 身内を送るつもりで納棺する
岐阜での出張、初めて一人で任された納棺。家族の涙が、自分の原点となった日。- 第2章 ありがとうが疑いになった日
感謝として受け取った寸志が、誤解を生んだ。納棺師としての信念が試された出来事。- 第3章 1年という期限を自分で決めていた
最初から決めていた「1年間の修業」。納棺協会を卒業し、自分の道を歩き始める。- 第4章 ゼロから始めた 誰も頼れない道を自分で切り拓いた
遺品整理からの再出発。紹介も信頼もゼロの中、弘前で地道に始めた独立の日々。- 第5章 感情を抑えない葬儀を 誰かが始めなければと思った
コロナ禍で失われた感情の時間。「喜怒哀楽の家族葬®」という言葉に辿り着いた理由。- 第6章 ここでようやく、父と話せた気がします
自宅での一日葬。式ではなく、対話の時間が、遺族の心を変えていった。- 第7章 魂の成長としての葬儀
葬儀は終わりではない。「感情に正直になること」が人の魂を深めていく。- 第8章 その日、母が若返ったと言われた納棺の記憶
「母が若返った」――遺族の言葉が、納棺師としてのすべての原点になった。- 第9章 なぜ、今この葬儀が必要なのか
形式ではなく感情を整える葬儀へ。時代が変わり、必要とされている理由。- 第10章 ご家族の声が教えてくれたこと
「こんなに心が動いたお葬式は初めて」──遺族の言葉が、すべての証明だった。- 第11章 これからの供養と、心の居場所について
葬儀は、生きていく人の“心の居場所”をつくる時間。送り方が、生き方を変える。- 終章 最後の時間に 人は 魂の美しさを取り戻す
人は亡くなるとき、もっとも美しい魂を取り戻す。その瞬間に寄り添う納棺師の祈り。▶ ご相談・資料請求は
LINE公式アカウントはこちら(24時間受付)
前の記事へ
« 第7章│魂の成長としての葬儀次の記事へ
第9章│なぜ、今この葬儀が必要なのか »