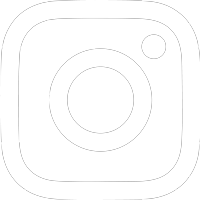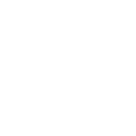第9章│なぜ、今この葬儀が必要なのか

なぜ、今この葬儀が必要なのか
形式ではなく感情に向き合う時代へ
納棺師として見てきた違和感
長年、葬儀の現場に立ってきて感じていたことがある
どんなに形式を整えても
どんなに立派な演出があっても
肝心の「心」が置き去りになっていることが、あまりにも多かった
悲しいのに泣けない
言いたいのに言えない
感謝も、後悔も、怒りも、口を閉ざしたまま時間だけが過ぎていく
そうした葬儀のあり方に、私はずっと疑問を抱いていた
家族が語り合う時間がない
打ち合わせでは、段取りと手配の話がほとんど
葬儀そのものは、静かに、滞りなく進められることが良しとされる
でも、終わったあとに遺族が残す言葉は、決まって同じだった
何も言えなかった
何も残っていない
ありがとうが宙に浮いたままだ
そう言われたとき、私は思った
もっと感情に向き合える葬儀が必要だ
形式ではなく、本音と向き合える時間が求められているのだと
喜怒哀楽を受け入れる葬儀
だからこそ、私は『喜怒哀楽の家族葬®』というかたちを打ち出した
泣いてもいい
笑ってもいい
怒ってもいい
黙っていても、構わない
出てくる感情は人それぞれで、正解なんてひとつもない
それでも、そのままの気持ちを置いていける場所をつくりたかった
葬儀という時間が、家族にとって
ただの儀式ではなく、感情の節目になってほしかった
時代が変わってきた
最近では、従来の葬儀に違和感を持つ人が少しずつ増えている
かつては当たり前だった形式や儀礼を、
今はもっと自分らしくしたい、意味のある時間にしたいという声が増えている
それは、ただの「簡略化」ではなく
「本音に戻ろう」という感覚なのだと私は捉えている
価格やプランではなく、
自分たちの想いをちゃんと伝えられるかどうか
そこに価値を置く人が、確実に増えてきた
葬儀とは、人生の集約ではなく、再出発の問い
私がこの仕事を通して確信しているのは
葬儀は終わりではなく、「問いのはじまり」だということ
あの人をどう送りたかったのか
本当に言いたかった言葉は何か
自分はこれから、どう生きていくのか
その問いを持てたとき
葬儀は、ただの儀式から、人生を見つめる時間へと変わる
だから今、この葬儀が必要とされている
世の中が揺れている今こそ
人のつながりが見えにくくなった今こそ
本当の意味で、心と向き合える葬儀が求められている
喜怒哀楽のすべてを、正直に出せる時間
それが、人生にとってどれほど大切か
私はこの仕事を通して何度も見てきた
そしてこれからも、それを届けていきたいと思っている
次章へ
次回は、実際に寄せられたご家族の声を通じて
この葬儀が、遺族にどんな意味を残したのかを記していく
相談したい方へ
- LINE公式登録はこちら
→ 「後悔しないお別れ」のために、大切な資料をLINEからすぐにご覧いただけます。
筆者について
樺澤忠志(とーたる・さぽーと0528代表/納棺師)
弘前市出身。父の死をきっかけに葬祭の道へ。今、感情を封じない「喜怒哀楽の家族葬®」を弘前で提供しています。
最期に「ありがとう」が届く時間を。
それが、私の仕事のすべてです。
まだ葬儀の予定がなくても、
今、LINEで「不安」を減らせます。「何を準備しておけばいい?」「費用は?」「誰に頼めばいいのか分からない」
そんな方へ、無料で個別にご相談いただけるLINE相談を開設しています。
まだお急ぎでない方も大歓迎です。葬儀を考える時、
費用でも、形式でもなく、
一番大切なのは、あなたがどんな想いで見送りたいかです。たった3つの質問に答えるだけで、
あなたに合った「後悔しないお別れの形」が見えてきます。
- STEP 1:LINE公式アカウントを友だち追加
- STEP 2:メッセージで「相談希望」と送るだけでOK
- STEP 3:対話形式で、気持ち・状況・準備を丁寧に伺います
▶ お電話でも相談可能です(24時間対応)
0172-82-2078
喜怒哀楽の家族葬® 樺澤忠志の記録|全12章
これは、ひとりの納棺師が歩んできた12の記録。
「形ではなく、感情に向き合う葬儀」を信じてきた私の原点と、実践と、これからの話です。
- 第1章 身内を送るつもりで納棺する
岐阜での出張、初めて一人で任された納棺。家族の涙が、自分の原点となった日。- 第2章 ありがとうが疑いになった日
感謝として受け取った寸志が、誤解を生んだ。納棺師としての信念が試された出来事。- 第3章 1年という期限を自分で決めていた
最初から決めていた「1年間の修業」。納棺協会を卒業し、自分の道を歩き始める。- 第4章 ゼロから始めた 誰も頼れない道を自分で切り拓いた
遺品整理からの再出発。紹介も信頼もゼロの中、弘前で地道に始めた独立の日々。- 第5章 感情を抑えない葬儀を 誰かが始めなければと思った
コロナ禍で失われた感情の時間。「喜怒哀楽の家族葬®」という言葉に辿り着いた理由。- 第6章 ここでようやく、父と話せた気がします
自宅での一日葬。式ではなく、対話の時間が、遺族の心を変えていった。- 第7章 魂の成長としての葬儀
葬儀は終わりではない。「感情に正直になること」が人の魂を深めていく。- 第8章 その日、母が若返ったと言われた納棺の記憶
「母が若返った」――遺族の言葉が、納棺師としてのすべての原点になった。- 第9章 なぜ、今この葬儀が必要なのか
形式ではなく感情を整える葬儀へ。時代が変わり、必要とされている理由。- 第10章 ご家族の声が教えてくれたこと
「こんなに心が動いたお葬式は初めて」──遺族の言葉が、すべての証明だった。- 第11章 これからの供養と、心の居場所について
葬儀は、生きていく人の“心の居場所”をつくる時間。送り方が、生き方を変える。- 終章 最後の時間に 人は 魂の美しさを取り戻す
人は亡くなるとき、もっとも美しい魂を取り戻す。その瞬間に寄り添う納棺師の祈り。▶ ご相談・資料請求は
LINE公式アカウントはこちら(24時間受付)
前の記事へ
« 第8章│その日、母が若返ったと言われた納棺の記憶次の記事へ
第10章│ご家族の声が教えてくれたこと »