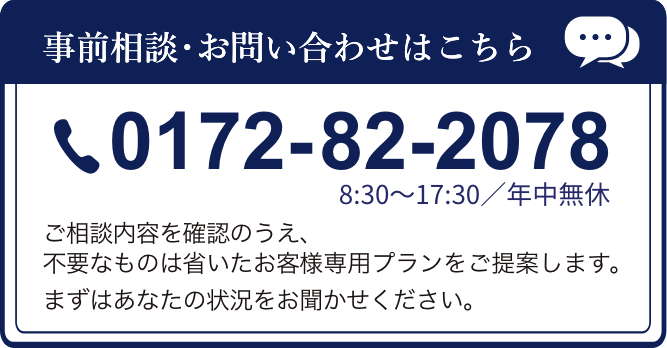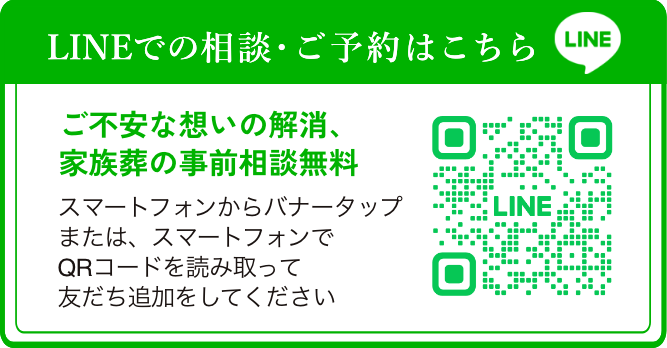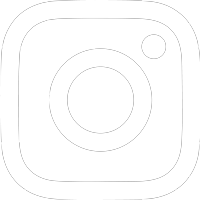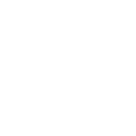白い家に黒い遺影。家族が見つけた処分しない供養という選択

遺影は処分すべき?
「処分するのは違う気がする」その小さな違和感が、家族の心をつなぎました。
白いリビングと黒い遺影 ある家族の会話から
「遺影写真、もう処分してもいいと思うの。」
新しい家に引っ越したばかりのご夫婦が、静かにそう話されました。
明るい木目と白を基調にしたリビング。そこに置く予定のモダン仏壇は、やわらかく上品なデザインでした。
けれども葬儀のときに使った黒い額の遺影だけが、どうしても空間の雰囲気に合わないように見えたのです。
「家の雰囲気が違ってしまって…」
そう語るお母さまに、娘さんは少し沈黙しました。
「確かに、合わないのはわかるんです。でも、処分してしまうのは違う気がして。」
部屋に流れる空気には、やさしさと少しの寂しさが混ざっていました。
親世代はけじめをつけたいと思い、子世代はまだ心の中で故人とつながっていたい。
どちらも正しい気持ちでありながら、供養の言葉が少しだけすれ違っていました。
なぜ親世代は「遺影を処分したい」と感じるのか
近年、リビング仏壇やモダン仏壇を選ぶ家庭が増えています。
住まいのデザインに合わせて、暮らしの中に自然に祈りを取り入れるスタイルが定着してきました。
一方で、昔ながらの黒縁の遺影は明るい部屋には重く見えがちです。
親世代が「処分したい」と思う背景には、いくつかの心情が隠れています。
新しい家に合わせたいという美意識
毎日見ると悲しみが蘇るため整理したいという気持ち
忌明けを過ぎた今こそけじめをつけたいという意識
つまりこれは冷たい感情ではなく、悲しみと生活のバランスを取ろうとする自然な心の動きなのです。
子世代の違和感の正体
一方で、子世代が「違う気がする」と感じるのは感情論ではありません。
遺影は記憶とつながりの象徴であり、心理学的にも人を支える力を持ちます。
遺影を残すことで故人が近くにいると感じられる
目にすることで思い出が穏やかに整理されていく
遺影をなくすと再び喪失感が強まる
日本グリーフケア研究会の調査では、遺影を手放した人の六割が「寂しさが再燃した」と答えています。
遺影を残すことは悲しみを断ち切るのではなく、やさしく受け止める時間を持つ行為なのです。
処分ではなく「整えて残す」という選択
この家族の場合、私はこう提案しました。
「遺影を捨てるのではなく、今のお家に合う形に整えてみませんか。
仏壇の中で大切に保管して、法要や節目の時にだけ取り出して飾る形です。」
遺影そのものは残し、額縁を紙製の軽いフレームに変える。
白い部屋にも調和し、掃除や保管もしやすい方法です。
処分という言葉を使わずに心と空間を整理する提案に、娘さんは安心した表情を見せました。
お姑さんも静かに頷き、「これなら大丈夫かもしれない」と小さくつぶやかれました。
捨てるでも固めるでもなく、整えることで想いを残す。
それが今の時代に合った新しい供養の形なのです。
世代をつなぐために必要な言葉
親世代は伝統と形式を大切にし、子世代は日常の中で自然に祈りたいと願う。
この違いは価値観の対立ではなく、祈り方の言語の違いです。
家族の中に一人でも「どちらも正しい」と受け止める人がいれば、
供養の形は優しくまとまります。
「お母さまの思いも、この形の中に残っていますよ」と伝えるだけで、心の距離が少し近づくこともあります。
現代の家と祈りの再設計
仏壇の形が変わっても、供養の本質は変わりません。
それは「故人を想う心を、暮らしの中に残すこと」です。
白いリビングに調和するモダン仏壇
節目のときにだけ出す遺影
家族が穏やかな気持ちで手を合わせられる空間
そうした工夫の一つ一つが、現代の祈りのかたちをつくっています。
終わりに 形を変えても想いは残る
葬儀が終わっても、悲しみはすぐには癒えません。
けれど、供養の形を自分たちの暮らしに合わせて整えることで、
悲しみは少しずつ「やさしい記憶」に変わっていきます。
遺影を処分する前に、一度立ち止まって考えてみてください。
どうすれば、故人を想い続けられる形にできるか。
形が変わっても、想いは確かに残ります。
それが今を生きる私たちにできる、心を残す供養です。